GWも明け、いよいよサツマイモの植え付けシーズン到来!今回はタイトルの通り、あらかじめ肥料を施していたエリアと無施肥(レンタル畑のため、前の方の肥料が残っている可能性はあります)のエリア、それぞれに植え付け成長具合や収穫結果にどう影響するかを見ていきたいと思います。
今回は「植え付け編」です。「肥料を入れるとサツマイモはどう変わるのか?」「無肥料でも育つって聞くけど、実際はどうなのか?」また、「植え付けは水平、斜め、垂直とあるけどどう違うのか?」こちらについて畑で、しっかり確かめてみようと思います。
今後の生育の様子もレポートしていきますので、興味のある方はぜひお付き合いください!
サツマイモは肥料なしでも育つといわれているが、堆肥は必要なのではないか
サツマイモは「やせた土地でも良く育つ」と言われており、むしろ肥料ありで育てた際の懸念点としては「ツルボケ」の可能性があるため、肥料を少なく育てるのが基本のスタイルと思われます。
一方、堆肥はどうでしょうか。堆肥にも栄養成分は含まれますが、肥料としての働きよりも「土づくり」としての働きが大きいです。サツマイモは排水性、通気性が良いことで肥大化につながるため、堆肥は十分にすきこんだほうが大きなサツマイモが収穫できると考えます。
つまり、「肥料は少なく、堆肥は入れる」がサツマイモを育てる上では重要になるのではないでしょうか。
表にまとめると次のようになります。今回は左上の「肥料+堆肥」、右下の「肥料も堆肥もなし」、の2パタンを選択。これを見るとわかりますが、「堆肥のみ」が最もリスクが少ないのかも。こちらについては今回の結果をもとに来年チャレンジしたいと思います。
| 堆肥あり | 堆肥なし | |
| 肥料あり(少なめ) | ツルボケリスクあり 畝を3つ作成 | ツルボケリスクあり 排水性リスクあり 今回不採用 |
| 肥料なし | リスクなし? 来年はここを実験したい | 排水性リスクあり 畝を1つ作成 |
土づくりについて(堆肥・肥料はいつもの3種)
それでは、続いて土づくりについてです。土づくりはいつも通り下記の3種類を使っています。施肥量を計測できていませんが、感覚としては少なめを意識して施しました。
- 牛糞堆肥:土の排水性向上のため
- 鶏糞:栄養分補填のため
- 米ぬか:微生物の活性化のため
これらを4/26に畑に鋤きこみ、3週間ほど休ませ土になじむのを待ちました。肥料をすきこんだエリアとしては下記の赤枠の箇所でこちらに3畝を今回作り、のこり1畝を肥料なしとしてこのすぐ隣に畝立てしました。

植え付け実践!植え方は「芋の数」を重視
いよいよ芋の植え付けです。サツマイモは肥料の状態に加え、植え付け方でも収穫量に差が出るといわれており、主には下記の3種類があります。今回はこれらのうち、芋の数を多くすることを重視し、水平と斜めを選択しました。
| 植え方 | 特徴 | サツマイモのなり方 | オススメのユースケース |
| 水平植え | 苗を寝かせるように植える | 芋が横方向に広がってつく。比較的数が多く、細めの芋になりやすい。 | 小さくても良いのでたくさんの芋を収穫したいとき |
| 垂直植え | 苗を真っすぐに立てて植える | 芋が苗の根元付近に縦方向にまとまりやすく、太くなりやすい。 | 大きい芋を収穫したいとき |
| 斜め植え | 一番ポピュラー。斜めに差し込む | 芋がバランスよくつく。形もそろいやすく、管理しやすい。 | 量もサイズもバランスよく収穫したいとき |
最終的な畝の様子がこちら。奥から3畝が肥料と堆肥を鋤きこんでいた畝、一番手前が何もなしの畝。
また、奥の2つが水平植え、手前の2つが斜め植えで植え付けを行いました。
畝幅はおよそ50センチ、株間は40センチ、高さ20センチくらいで畝立てしています。

今回植えたサツマイモ「べにはるか」「べにあずま」は祖父母と孫の関係
今回はホームセンターで「べにはるか」と「べにあずま」の2つを購入しました。

畑のスペースから15本程度で探していたので、ちょうど7本ずつ入っていたので好都合でした。「紅はるか」はしっとり、ねっとり系で甘みのある、最近の焼き芋ブームでも人気の品種です。「紅あずま」はホクホク系で昔ながらのサツマイモ、といった印象です。というのも、「紅あずま」は「紅はるか」にとって祖父母の関係になっているので食文化の変化もうかがうことができますね。
以上、サツマイモの植え付け編でした。
今後は肥料の有無、植え付け方の違いでどのような成長の差が出てくるか、機会をみて記事にしたいと思います。ご期待ください。
本日の畑
最後に畑の様子です。過去記事(イモの植え付け(ヤツガシラ、丹波つくね芋))で植えたヤツガシラとつくね芋の芽が出てきました。植え付けたから気温の乱高下がひどく、ひとつも芽が出なかったらと心配していましたが、一安心。これからも見守っていきます。
ヤツガシラの芽。しっかりと太い茎で葉っぱも肉厚。

つくね芋の芽。こちらはようやく頭が出た感じでまだまだ小さい。

本日はここまで。本日もご覧いただきありがとうございます。

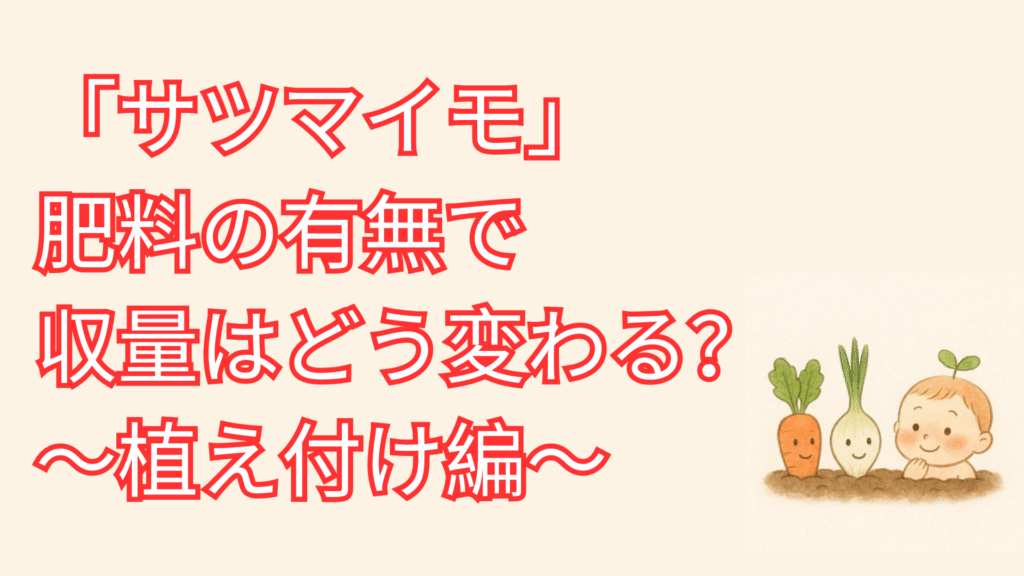
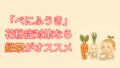

コメント