昨年の12月から育て始めている1年目の若いスイートスプリング。猛暑の中でも元気に夏芽をつけ、葉っぱの密度が増えてきました。この夏芽を今回どうするか、プランターで育てているスイートスプリングの現在の成長具合と育て方について紹介します。
スイートスプリングを始め、果樹が花芽をとなるのは春芽のため夏芽は不要、刈ったほうが良いという意見もありますが、今年は刈らずに残すことにしました。その理由についても触れていきます。最後までご覧いただけますと幸いです。
2024年12月に買ってから8か月、苗は元気に成長中
買ってから春先までは幹も細く、根も短く不安な状態でした。

当時は購入後すぐに10号プランターに植え替えを行ったのですが、ぐらつきがあったため4月に8号プランターに移植を行いました(元気のないスイートスプリングの植え替え)
現在はぐらつきもなく、しっかりと根が張っている予感がしています。
4月以降から気を付けているポイントは下記の
- 水やりは1日1回以下
- 追肥は油かすを少々
- 虫のチェックを入念に
水やりの頻度は少なめでもOK
水やりを毎日毎日かけるのは良いことのように感じますが、春先のまだ気温も低く、光合成も活発に行われていない時期はプランターでも土中水分は1日では使いきらず翌日でも水分が残っていることが多いです。このタイミングでさらに水をかけると水分過多、根腐れを引き起こす可能性があります。水やりはプランターを持ったり揺すったりして軽さを感じた時にかけるようにしましょう。
追肥は月に1回程度、油かすと米ぬかを少々
4月に植え替えをしたタイミングで元肥に鶏糞を少し、米ぬかを少し入れていました。現在は追肥を月に1度、菜種油かすと米ぬかを少し振りかけるようにしています。一時期追肥していなかったのですが、葉の色が薄くなり始めたため追肥するようにしました。実をとるころにはリン酸が多めの肥料を上げたいと思いますが、まだ1年目の若い株のため、まずは葉を育てようと思い窒素成分が多めの油かすを与えています。
幼虫がいないか、毎日チェック
暖かくなり、庭を飛び回るアゲハ蝶を見かける頻度も増え、同時に若い芽では幼虫もよく見かけるように。そのまま放置するとせっかくの芽も食べられてしまいます。見かけたらすぐに取り除くようにしましょう。
孵化して間もないアゲハ蝶の幼虫は黒いため、緑の葉の上にいると目立ちます。幼虫がいるはずだ、という意識をもって観察すると見つけやすいです。特に葉に細かい黒い粒粒があると、それは幼虫の糞の可能性が高いです。糞を見つけた時には必ず本体がいますのでしっかりと探すことをオススメします。小さいうちは心理的ハードルも低いと思いますのでなるべく早く取り除けるように注意して観察しましょう。
夏芽の扱い方について。今回は残すことに。
7月中旬頃には花が咲き、夏芽がしっかりと育ち始めてきました。

来年の冬に実がつくのは今年の春芽であり、夏芽に実がつくことは稀と聞きます。そのため、夏芽は刈ってしまうことが多いのですが、今年の夏芽はしばらく残しておこうと考えています。
果樹を収穫するまでの成長の流れ
スイートスプリングを始め、果樹が実をつけるまでの流れは下記のように成長します。
- 今年の春に芽がのびる(春芽)
- 秋頃に春芽から花芽に分化
- 翌年の春に花芽から花が咲き始める
- 結実して冬に収穫♪
一般的な柑橘類の果樹は春頃に伸びた芽から花芽ができ、収穫につながるため、春芽を大事にしようといわれています。一方、夏に伸びてきた夏芽は2番の工程で花芽に分化する可能性が低いです。これが夏芽は刈ってしまうことが多い理由となります。
今年の夏芽は刈らないことにした理由は樹の成長
さらに夏芽は若いため幼虫には食べごろの硬さ。幼虫がつくことも多い季節、虫の対応も大変になりますが今回はあえて夏芽を残すことにしました。
この理由は「株を大きくする年にしたい」という思いからです。前半でお話しした通り、12月に買ったときには根張りも悪く、4月にも幹にグラつきがあって不安定な状態でした。最近になり、ようやく根が安定してきましたが、まだまだ幹も太く成長させたい。
そのためには少しでも光合成を促進する葉っぱを維持したい。虫のチェックは必要となるけれど夏芽も活用しよう、と決めました。
春芽には花も咲きましたが、まだ花を育て、実を突かせるだけの力のない株ですので、今回は花もすぐに落としてしましました。
その効果なのか、株全体の色付きもよく、元気に育ってくれています。株元も緑色になってきて、幹が太くなっていることがうかがえます。
今年の秋に花芽ができ、来年には1つくらい実ってくれるといいな、と思いつつ、今年の夏はしっかり樹を強くさせるように育てていきたいと思います。
まとめ
今回はプランターで育てている1年目のスイートスプリングの育て方について紹介しました。同じく若い柑橘の果樹を育てている方の参考になればうれしいです。
本日も最後までご覧いただきありがとうございます。

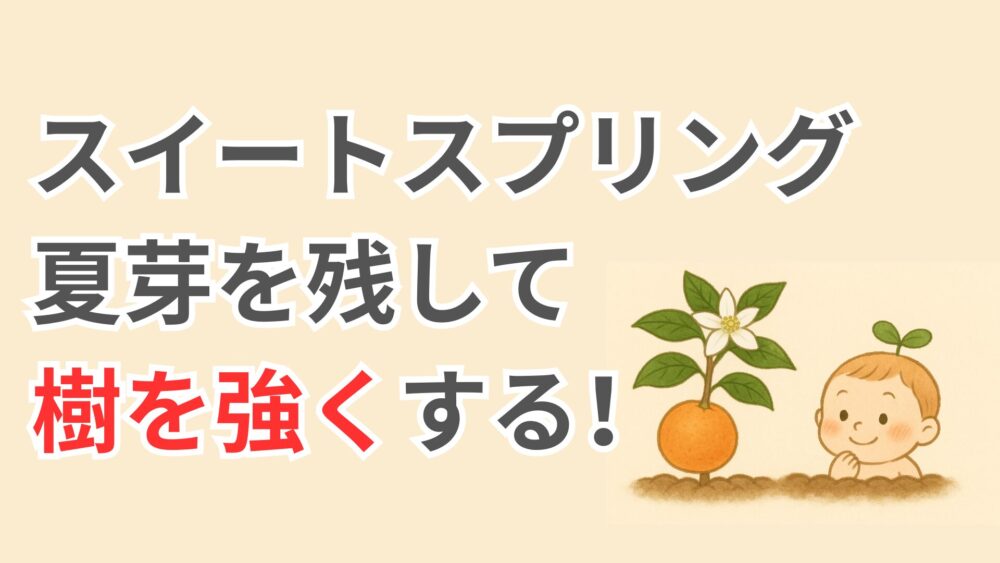

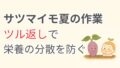
コメント